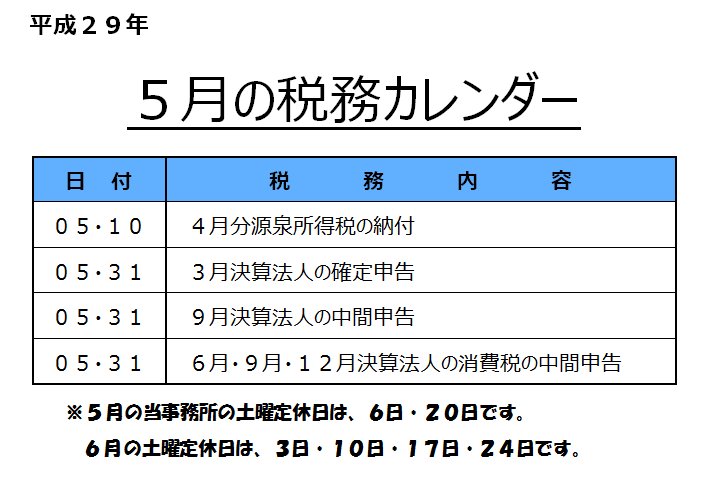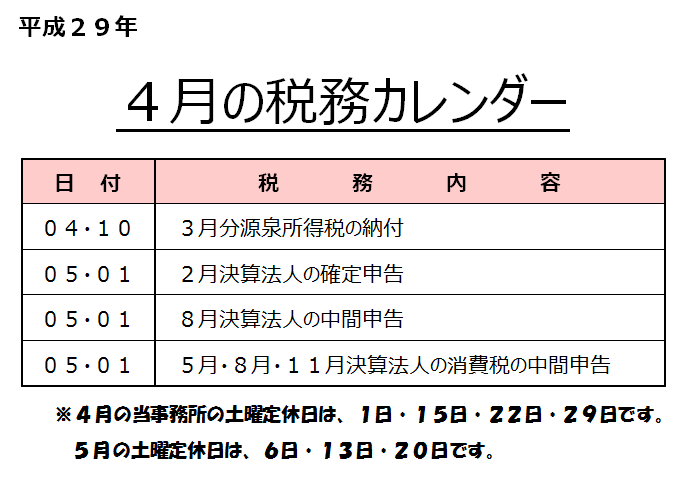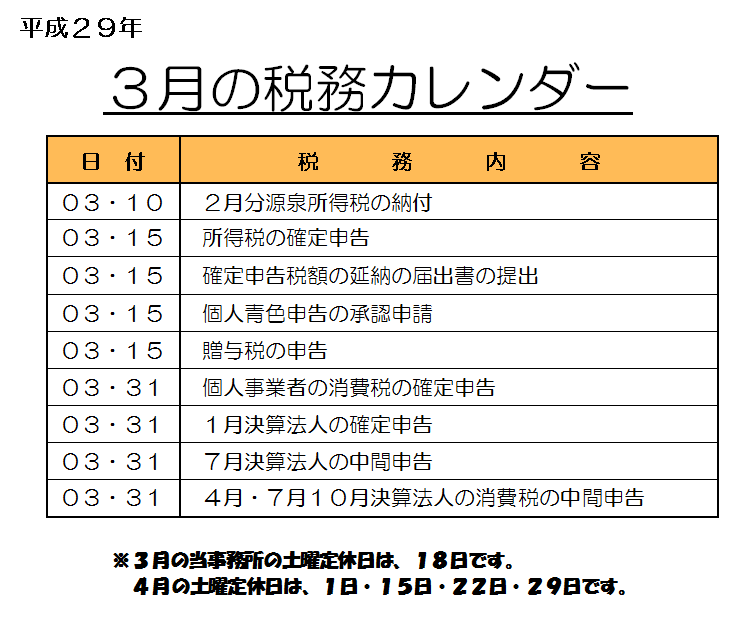今週の考える言葉「人の力」
考える言葉
人の力
最近購入し、一気に読み上げてしまった本の中に、『孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごいPDCA』(三木雄信 著、ダイヤモンド社)というものがある。今年の2月に初版、すでに第5刷発行となっているので、かなりの売れ筋なのだろう・・・。
ソフトバンクは、創業からわずか30数年で8兆円企業へと成長した。カリスマ経営者・孫正義が率いる組織だからこそ、なし得た成果だと思うだろうが、ソフトバンク躍進の最大の秘密は、「高速PDCA」思考の徹底実践にこそあるとし、その考え方を分りやすくまとめた良書である。
ソフトバンク流「高速PDCA」の特徴は、スピードとタイミングの重視であろう。それを、「ソフトバンク3原則」と呼んで、次のように紹介している。
① 思いついた計画は、可能な限りすべて同時に実行する
② 1日ごとの目標を決め、結果を毎日チェックして改善する
③ 目標も結果も、数字で管理する
「PDCA」という経営サイクルの仕組は、誰もが良く知っている経営手法である。しかし、その手法で結果を出している組織や個人は、やはり、一味も二味も違う。自分流というか、考え抜いて、実行し、自らの哲学にしている。一読の価値あり・・・。
さて、今日のテーマである“人の力”について、である。この本の中で、「“人の力”の借方」として、孫正義の凄さを紹介している(第6章)。
なぜ“人の力”を借りるのか?孫さんの答えは明確、「自分一人できることなど、たかが知れている」。“人の手”を借りれば、一番手っ取り早く成功できる、つまり結果を出せる!という。「やる!」と決めて動き出して、“人の力”を借りる。とに角、結果を出すことに専念している。
また、孫さんは、人を使うのが実に上手いという。秘訣の一つは、素直さ!「相手の肩書きやキャリア、年齢や経験を問わず、自分にとって有益だと思う情報やノウハウを持っている人のアドバイス」を、素直に傾聴するという。
さらに加えると、熱意!孫さんは若い頃から、知りたいことがあれば自分から情報や知恵を取りに行っていたという。連絡を取って、相談に行けば、相手は「この人は本気だな」と、その熱意を感じて、懇切丁寧に教えてくれるし、力を貸してあげたくなるものだ。
もう一つ加えるとすれば、孫さんのビジョン・志の確かさだろう。そして、「やる!」ことへの信念・・・。
「素直さ、熱意、ビジョンの確かさ」 改めて自問自答したいと思う。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」