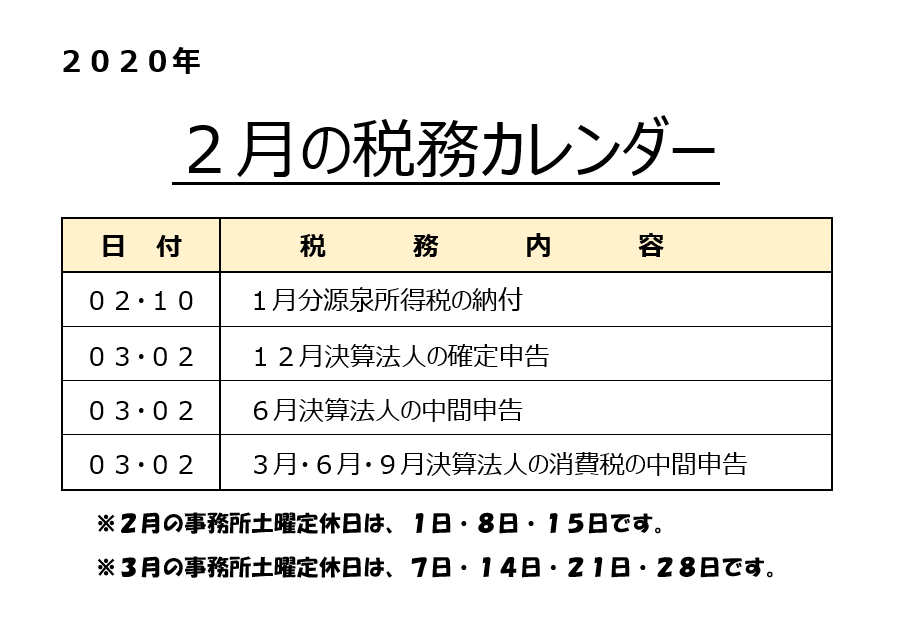今週の考える言葉「知的好奇心」
考える言葉
知的好奇心
先週(2月5日)、恒例の『IG新春セミナー』を講演会(第一、二部)及び懇親会ともに、盛況のうち無事終了することができた。
講演第一部は、小生が「再現性こそ真の実力」というテーマで担当し、「経営における再現性を高めるためには、何をなすべきか」について話をさせて頂いた。続く第二部は、小坂達也氏による「日本を支える偉人たちの帝王学」というテーマ。『古事記』に出てくる八百万の神の話を通して、日本文化を軽妙に伝える話しぶりは絶妙な感があり、久々に“知的好奇心”を駆り立ててくれた・・・。
「君(キミ)が代」は、イザナ“キ”とイザナ“ミ”が結ばれたラブ・ソングの詩だった。「君が(愛し合い、誘い合う男と女が)」「代(時代を超えて)」「千代に八千代に(永遠に、生まれ変わってもなお)」「さざれ石の巌となりて(その家族や親戚、仲間と結束し、団結して)」「苔のむすまで(子を養い育てながら繁栄していこう)」 「神世の代から重なり合う縁を大事に、和をもって繁栄していこう」という、まさに今の時代に求められている持続可能性(sustainable)の真髄を教示してくれていると思う。
氏の講演を聴きながら、学生の頃に、ある先輩がアドバイスしてくれた“知的好奇心”という言葉を思い出していた。
「学者に限らず、どんな職業であろうと一流と言われる人たちはみな、“知的好奇心”が旺盛だ」と・・・。だから、「これから先も“知的好奇心”だけは忘れてはだめだ。そのためには、読書を深めることだ」と、酒を飲みながら語ってくれたものだ。
学生の頃は、文学作品や哲学書的な本を好んで読んでいたが、社会人になってからは職業柄か、専門書的な本が圧倒的に多くなった・・・。最近は、仕事以外のことに関して“知的好奇心”を向ける必要があると感じていたところ、『平家物語(一、二、三)』(木村耕一 著)と出逢い、一気に読み上げたところである。
思った以上に読み易く、面白かったので『意訳で楽しむ古典シリーズ』(1万年堂出版)の出版物を読み漁ってみようと思っていたところである。
『古事記』に関しても、もっと知りたいと考えていた矢先に、小坂氏がそんな活動をしていると知り、さっそく連絡を取って、講師を依頼した次第である。すごく、いい切っ掛けを頂いたような気がする。今度、いろいろある『古事記』の解説本を読み漁ってみた
いと思う。
『日本の神さま 開運BOOK~あなたの守護神を教えます』(小坂達也 著)は、自分の守護神が分かると同時に読み易いので、ぜひ一読願いたいと思う。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」