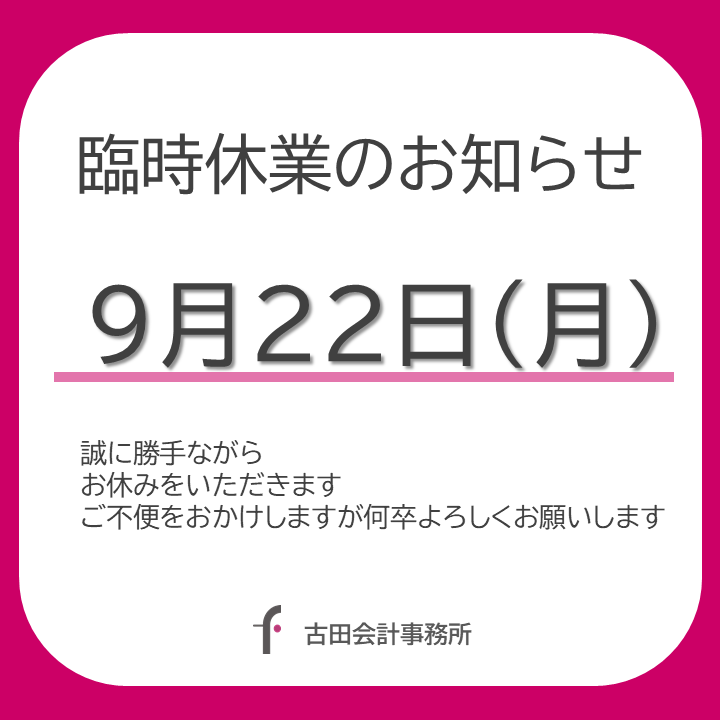七つの特性
「どんなに勉強して、知識を深めても、それだけでは成功者にはなり得ない。成功を手にするためには行動が不可欠である」と、昔からよく耳にした言葉だ。
確かに、私の知る限りにおいても、成功した人たちが、普通の人にないものを持っているとするなら、それは行動する能力だろう。では、卓越した行動力はどこから生じるのであろうか……。
これも書棚を整理しているときに、目に止まった本で、『一瞬で自分を変える法』(アンソニー・ロビンス 著)というのがあった。もう10年前に購入した本である。
その中に、「情熱を持って成功に向かって驀進する人たちには“七つの特性”が備わっている」という下りがあったので、どんな特性か、一つひとつ考えてみたい。
➀ 「情熱」・・・寝食を忘れ、とりつかれたように打ち込む。情熱は元気の源で、あらゆるものに意味を与えてくれる。
② 「信念」・・・魔法の力である。「自分にはできる」と信じていることは、やがて実現する。
③ 「戦略」・・・持てるもの(情熱や能力など)を体系的にまとめ上げるのに必要なものである。
④ 「明確な価値観」・・・生きていく上で、何が正しく、何が間違っているかを判断するための明確な信念体系である。
⑤ 「高エネルギー」・・・エネルギーに満ちた人は、じっとしていられない。チャンスを逃さないどころか、自らチャンスを生み出していく。
⑥ 「対人関係力」・・・自分の味方を増やす、人と絆を築く類まれな能力を持っている。心を通い合わせることができるのだ。
⑦ 「コミュニケーション力」・・・他人、そして自分と、どうコミュニケーションをとるかが、最終的には私たちの人生の質を決めるのだ。
以上である。
私たちの経済環境は、バブル崩壊後、「失われた10年」があっという間に「失われた30年」となった。デフレ経済が続く日本……。先だって、海外に行った時でも、ショッピングに出かけたが、買う気にならなかった。なぜ?日本で買ったほうが安く買えるからだ。
今や日本の経済は、放っておけない状況にある。「失われた40年」ではなく、「崩壊する10年」になる可能性があるとも言われている。
「仮説~実践~検証」のサイクルをまわし、自らの手で未来を創造する覚悟が問われている。行動のための“七つの特性”を自問自答してみたいと考える。