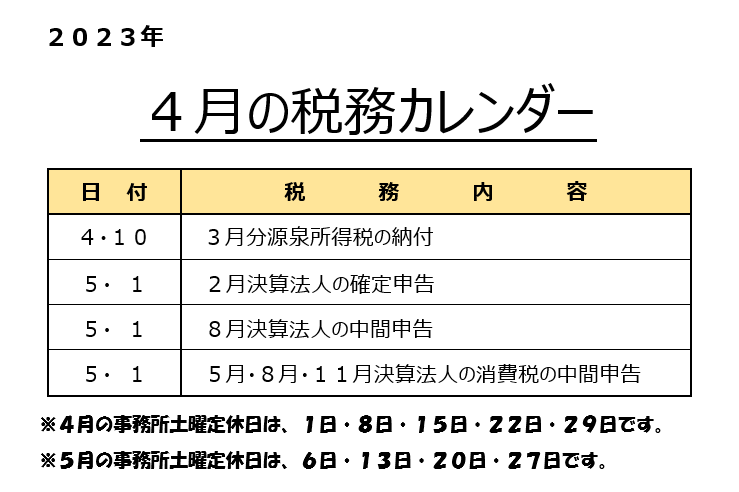今週の考える言葉「洞察力」
考える言葉
洞察力
変化が激しい今日的な環境において、経営者に求められる資質としてよく、① 洞察力、② 判断力、③ 実行力の三つが挙げられる。
今回、その“洞察力”について考えてみたい。
“洞察力”とは、「物事の本質を見抜く力」だという。言葉を変えていうと、「見えていない部分」まで見抜いていく力だといえよう。確かにそう考えると、今の時代環境には
必要な資質の一つであるといえよう。 “洞察力”のある人って、どんな特徴があるだろうか。
① 客観的な視点から多角的に見るとこができる
② 相手の仕草や言葉に敏感で、用心深い
③ あまりしゃべらず、人をよく観察している
④ 直観力に優れ、勘がよく当たる
⑤ 自分の感情を上手くコントロールできる
などがある。
では、“洞察力”を鍛えるためにはどんな心がけが必要だろうか。
① 日頃から周囲をよく観察すること
② 自分の先入観で物事を捉えないこと
③ 過去の失敗や経験を記録し、分析すること
④ 新しい価値観も素直に受け入れること
⑤ 「なぜ」を問う習慣を身につけること
⑥ 何事にもチャレンジして経験を積むこと
などが挙げられるが、大切なことは、何事にも問題意識をもって取り組むことだと言えるだろう。
冒頭に述べたように、変化が激しく、先行きが不透明な時代である。見えないものを感じ取り、本質を見抜く“洞察力”は、ますます重要なスキルとなってくだろう。もちろん、すぐに習得できるものではないので、日々心掛けて積み重ね、少しずつ鍛えていくしかないと思う。
さらに大切なことは、身につけた“洞察力”をどう生かすかの問題がある。
“洞察力”を高めるメリットとして、問題解決能力の向上につながるし、コミュニケーション能力の向上につながることは間違いない・・・。
もう一つ加えておきたい重要なことは、その洞察力をもって相手の立場を熟知し、思いやる心を持つことだ。それによって、人間関係が良好になり、生産的になれる。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」