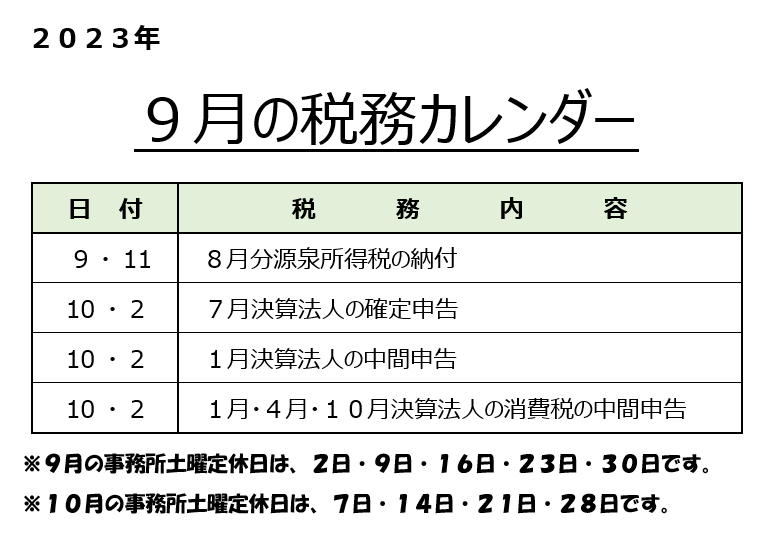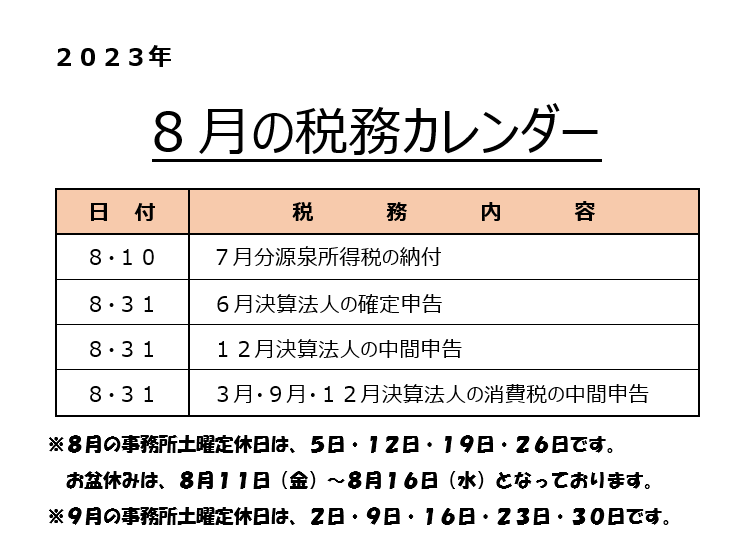今週の考える言葉「学ぶ心」
考える言葉
学ぶ心
『NN構想の会・第23回全国大会』(9月7~8日)を無事に終えることができた。2019年以来、4年ぶりに、本来の姿での開催である。
その間、2020年は中止、21年と22年はオンラインでの開催だったが、もうすっかりNN大会の馴染みと会場となった『ホテル椿山荘東京』で、みんなが集まっての大会はやはり一味違う趣を感じることができた。
今大会のテーマは、『セルフマネジメントの徹底~健全な判断力を磨こう』である。アフターコロナという経済環境下で、今後の経営の舵取りや仕事への取り組み方を考えたとき、『セルフマネジメント』という考え方が一つのキーワードになると確信し、テーマとして掲げた。
第一日目の最初は、基調講演。
『「ソニー再生」変革のモチベーショナル・リーダーシップ』と題して、平井一夫氏が「リーダーシップの要諦は、IQよりもEQを高めることだ」という持論をベースに、経営者としてのモノの考え方、価値観の重要性を説き、MVV(Misstion、Vision、Value)の共有ができているか、そのためには現場に足を運び、コミュニケーションを大事にしたいと語ってくれた。
そのあと、パネルディスカッション第1部「未来会計の実践とJa‐BIGインフラの使命とは」、第2部「セルフマネジメントの要諦」と続いた。
それぞれ、パネリストは会員や支持団体の方々から選出され、職業会計人の社会的な使命や業界のあるべき姿について大変有意義な議論が展開され、聴き応えがあったと思う。
そして、大会一日目の最後は「情報交流パーティー」。4年ぶりの企画であったが、お酒を飲み交わし、談笑する姿には空白の期間を感じさせることなく、盛り上がっていたと思う。
大会二日目は、分科会。
NNの支持団体が協力し合い、それぞれのテーマを掲げ、4会場で7つのテーマで分科会が開かれた。同時開催なので、すべてを聴くことができなかったが、支持団体の思いが伝わったのか、いずれも大変好評だったようだ。
教える側も学ぶ側も、会計業界を良くして、より社会貢献したいと思いは一つ。共創のためのNN(ネットワークのネットワーク)、そのステージをより充実したものに進化させていき、未来への礎を創っていける会計業界にしたいと思う。
そのためにも、“学ぶ心”を大事にし、持ち続けたいと改めで感じた2日間であった。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」