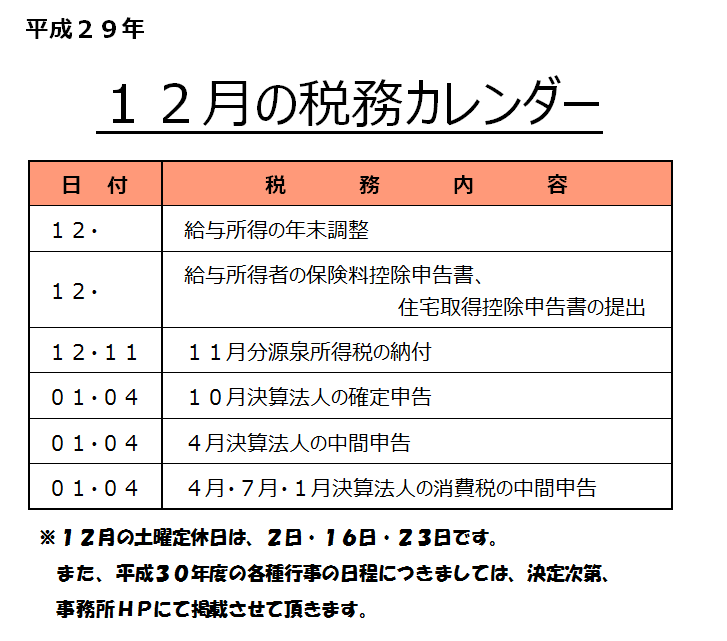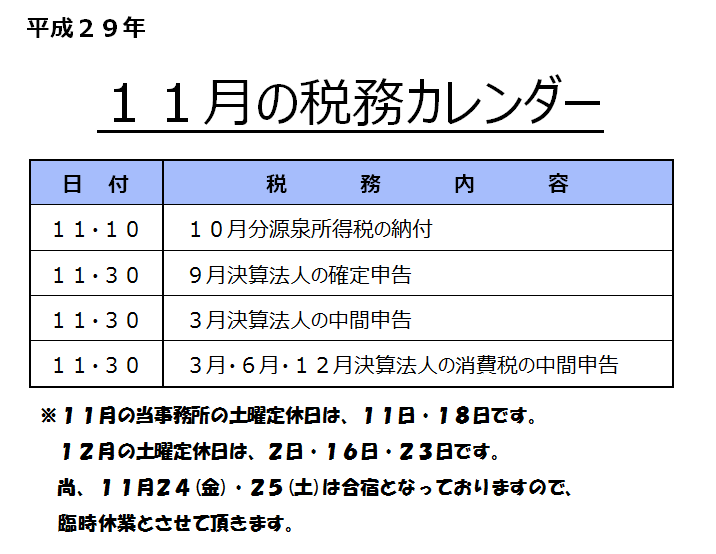今週の考える言葉「時流」
考える言葉
時流
「流れに掉さす」という言葉がある。「機会をつかんで、“時流”に乗る」という意味である。
ご存じだろうか?この言葉の意味についてアンケート調査をしたら、6 割がたの人が逆の意味(「時流に逆らう」)だと思っていたそうだ・・・。ついでに言うと、「役不足」とは「力量に比べて、役目が不相応に軽いこと」をいい、「力不足」ではない・・・。
さて、話題をテーマに移そう。
“時流”とは、「時代の流れ。風潮、傾向」といった意味であるが、時代を形成する価値観がその流れをつくっているといえよう。
「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは変化に最もよく適応したものである」(ダーウィン)という言葉があるように、確かに“時流”を捉えたビジネス展開をしている企業の快進撃には目を見張るものがある。
最近、新たな成長戦略を描けず、現状維持あるいは衰退していく企業が多いと聞く。
さらに社会的問題としては、『大廃業時代の足音~中小「後継未定」127 万社!』(日経10 月6 日付)の記事が象徴するように、経営者の世代交代という事業承継の問題がある。
世代交代を済ませて、第二創業を託された新経営者から受ける相談に、「新たな成長戦略をどう構築したらいいのだろうか?」というのがある。そのときに思考すべき大きな課題の一つは、まさに“時流”であろう。
① 先ずは、世の中あるいは業界の“時流”を見極めること。
いつの時代にも、先駆的な役割を担う勢力がある。また、この世に逆境が生じたときにはそれに抵抗する勢力(イノベーター)が生まれ、新たな環境をつくっていき、時代は動いていく。その“時流”を、どう見極め、捉えるかである。
② 次に、“時流”に乗るための戦略を持つこと。
ここでいう戦略とは、時流を見極め、それを活かすためのオリジナルな思考であり、それを実行に移すためのシナリオだと考えていい。
以上の二点から、ビジネスチャンスを捉え、ビジネスモデル(儲かる仕組み)を再構築していくと、自ずと新たな成長性が浮き彫りになってくるはずだ。
“時流”の根底には、社会問題の本質があるような気がする。例えば、少子高齢化人口減少が進む日本では、付加価値の高い仕事のスタイルを身につけていく必要がある・・・。
そこが一つの“時流”になっていくのであろうと考える。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」