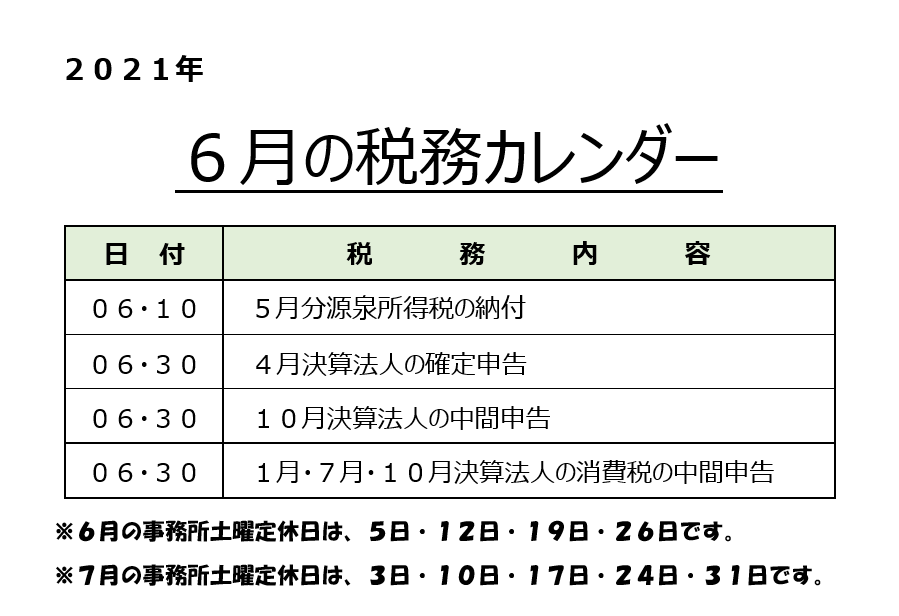今週の考える言葉「プロの時代」
考える言葉
プロの時代
前回の“考える言葉”シリーズ(21‐20)で、『レスの時代』について紹介した。
その記載があった『コロナ後に生き残る会社 食える会社 稼げる働き方』(遠藤功 著)の著書の中に、もう一つ意義深い視点での内容があったので、それも紹介しておきたい。
それは、「コロナ・ショックは、ビジネス社会における“プロの時代”の幕開けになる」という指摘だ。つまり、滅私奉公的なサラリーマンは淘汰され、高度専門性と市場性を兼ね備えた「“プロ”が活躍する時代」になるという・・・。
「コロナ後の時代環境はどう変化していくのだろうか?」について、関心と同時に計りかねていた小生にとっては、示唆深く、有難いサゼッション(suggestion)である。
このサゼッションの前提には、世界経済が大きく縮む・・・。恐らく、「70%エコノミー」が妥当だという予測がある。「縮んだ経済」の中で生き残るためには、企業も身を縮めるしかない。
そのとき、「プロ」と「アマ」の差が歴然としてくるのだという。つまり、「プロ化するビジネス社会」とは、「人が生み出す価値には歴然とした差がある」という現実を認める社会のことである。
それと、“プロの時代”が進むに連れて、日本における人材の流動化は、急速に高まっていくと予測される。つまり、終身雇用や年功序列的な慣行は大きく変わっていくだろう。著者は、“プロの時代”の幕開けの中で、プロとして勝ち残っていくためには次の5つのパラダイムシフト(発想転換)が不可欠であるという。
①「社内価値」ではなく、「市場価値」で勝負する
②「プロセス」ではなく、「結果」にこだわる
③「相対」ではなく、「絶対」を目指す
④「他律」ではなく、「自律」で行動する
⑤「アンコントローラブル」は捨て、「コントローラブル」に集中する
以上である。世界経済が大きく縮む中で、著者が言いたかったことの一つは、職業や職種の視点からだけ見ていると、落とし穴にはまるということだ。大事なのは、どの職業であろうと、「その職業に従事する一人ひとりがプロなのか、アマなのか」ということである。
自分は何の「プロ」なのか?何の「プロ」を目指すべきなのか?いまこそ、自らに問い直す必要があると考える。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」
今週の考える言葉「レスの時代」
考える言葉
レスの時代
「コロナ後に世の中はどう変わっていくのだろうか?」ということを思考しているとき、出逢った本に『コロナ後に生き残る会社 食える会社 稼げる働き方』(遠藤功 著)がある。
その著書の中に、「コロナ・ショックは“レスの時代”の幕開けである」という面白い内容が記載されていたので紹介をしたい。
氏がいうには、コロナ・ショックは「福音(ふくいん)」だった・・・。なぜなら、結果として、「レス」という「新たな選択肢」を手に入れることができたからだという。
コロナによって私たちは行動自粛を余儀なくされ、否が応でもオンライン化やリモートワークを進めざるを得ない状況に追い込まれた。
しかし、それによって「ペーパーレス」「ハンコレス」はいうに及ばず、「通勤レス」「出張レス」「残業レス」「対面レス」「転勤レス」など、「レス」できるものが多いことに気づかされたのである。
「選択肢」が増えるということは、豊かになることである。同時に、これからは「複数の選択肢」を賢く使い分けていく時代になるということだ。だが、ここには一つの問題が出てくる。それは、賢く使い分けができる人とそうでない人の間に格差が生じるということだ。
著者はこの点について、次のように述べている。
「ポストコロナは、高度専門性を備え、市場価値のあるプロが大活躍する時代になる」と。つまり、上司の言うことを聞き、まじめに働くだけのサラリーマンは淘汰されるか、極めて低い賃金で働かざるを得なくなるということだ。
「スマートワーク」という言葉がある。どういう意味かというと、多様な働き方を採用し、生産性を上げ、効率的に働く「働き方」をいう。そして、それは「プロ」としてふさわしい新しい働き方である。
「スマートワーク」、つまりプロとしての「働き方」を身につけるには、次の二つの視点で「働き方」を見直す必要があるという。
① 一つは、「生産性」をいかに高めるか。
② もう一つは、「創造性」をいかに高めるか。
つまり、ムダを省き「効率よく働く」ことと、ユニークな発想と斬新なアイデアで「価値あるものを生み出す」ことはトレードオフではないということだ。
“レスの時代”とは、不要なものを「レス」すると同時に、新たな価値を創出してこそ、真の意味での「プロの仕事」だと評価される時代だといえよう。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」
今週の考える言葉「実行力」
考える言葉
実行力
先週末(5月14日)、『未来会計実践塾・第16回定例会』(Ja‐BIG主催)が開催された。
本来であれば、研修会場(東京)に集まり、泊り込みで行うのだが、コロナ騒動の中、残念ながらオンラインでの開催となった。
㈱日本BIGネットワーク(通称:Ja‐BIG)は、未来会計の事業化(年商1億円以上)を達成することによって、会計業界の先駆的役割を担うと同時に、中小企業のゴーイングコンサーンを下支えする社会的インフラを構築しようという志をもって、全国の職業会計人が共同出資をして設立したコンサルティング・ファームである。
2014年創業で、はや7年経つが、気になることが一つある。それは何かというと、会員間の格差である。つまり、未来会計を事業化するための成果を確実に積み上げているところと、そうでないところの格差である。
その事業化のためのビジネスモデルは体系化され、それを学ぶ機会(基本コース、実践コース、定例会など)も均等化されているにも関わらず、成否の格差が生じてくる。主催者側としては、いつも頭を悩ます課題の一つである。
格差の原因は、いろいろと考えられるが、最大の要因は学後の実践であろう。つまり、“実行力”の差である。
勿論、専担者個人の“実行力”が問われるのは当然であるが、新しい事業を立ち上げようとするとき、むしろ、組織としての“実行力”の有無を問うべきであろうと考える。
なぜならば、組織を構成するメンバーは、少なからず、組織風土の影響を受けるからである。では、「良い組織風土」とは、基本的に次のような特性を持っているといえよう。
①組織メンバーが進んで仕事をする環境がある。
②組織メンバーが互いに協力し合う環境がある。
③組織に問題が生じたとき、それをオープンにし、協力して解決する環境がある。
特に、トップの仕事とは、上記のような環境を整えることに重きを置いて経営の舵取りをするように心がけるべきであろう。
新規事業を立ち上げるということは、先を見て、未来に備えるということを意味している。トップのリーダーシップは勿論のことだが、組織全体としての取り組みが、その成果に大きな影響を及ぼすことは言うまでもない。
組織の課題に対して、真摯に取り組む“実行力”があるか否か、そして成果が出るまでやり続ける“持続力”が問われるのだと考える。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」
今週の考える言葉「経営チーム」
考える言葉
経営チーム
GWの間に読んだ本の中に、『未来を共創する“経営チーム”をつくる』(鈴木義幸 著)という著書がある。
この著書の冒頭に、次のような内容のことが書いてある。
『「会社は社長で決まる」というが、「会社は“経営チーム”で決まる」といったほうが、より現実にあっている』と。長いこと、エグゼクティブ・コーチングの仕事をしてきた著者の経験から所見であろう。
多様化した時代環境の中で、「企業の舵取りをどうしたらよいのか?」という経営課題に直面し、組織のあり方についても、様々な研究がなされている。
従来のピラミッド型の「階層型組織」(機械論的)における管理型経営では、時代の変化に適応できないとして、セルフマネジメントを前提とした「ティール組織」(生命体的)という新しい組織のあり方と同時に、自主的経営の重要性が言われるようになってきた。
そのような背景のもと、組織の経営を携わる経営陣が“経営チーム”として機能することの重要性を提案している。
著者は「チームとは何か?」について、次のように述べている。
「チームとは、チームとしての目標“を持っていて、共創していて、そして気持ちがつながっている」
つまり、① 達成すべき目標の共有化、② 共創によるシナジー効果、③ 価値(成果)への共感性。それらが、メンバーの共通認識としてあるか。では、“経営チーム”を進化させるために心得ておくべきことをまとめておきたい。
①対立(=お互いに違い)を活かすこと(創造のための対立)
②会議のバージョンアップ(良い会議とは何かを検討する)
③パーパス(=目的)の共有(社会的存在の意義を意識する)
④関係性へのチャレンジ(ルーチン化しないために、日々新たに!)
⑤「悪口」を他言しない(相手への不満は直接話す)
⑥外とつながること(新しい視点、意見を獲得する)
⑦フィードバックを受ける(外部の視点からフィードバックを得る)
⑧チームの理想について考える(最高のチームと何かを問い続けること)
不測の事態が起こりうるご時世・・・。そんな中、継続的な右肩上がりを実現していくには、トップの独壇場という訳にはいかない。
一人ひとりの衆知を集めて、未来を共創する“経営チーム”をつくりたいと思う。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」
【コロナ支援】営業時間短縮要請協力金【和歌山市】
その他お知らせ
和歌山市内における飲食店を運営事業する事業者の皆様に対し、和歌山県営業時間短縮要請協力金を支給します。
◆ 対象店舗
条件①、②どちらにも当てはまる店舗が対象になります。
① 食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を得て、営業する店舗
〇 飲食店:飲食店、喫茶店、居酒屋等
〇 遊興施設等:カラオケボックス、バー等
② 要請前において、通常の営業時間が21時から翌日の5時までの間に営業時間が含まれる店舗
◆ 対象期間
4月22日(木) ~ 5月11日(火) → 5/7に延長されました
変更後
第1期:4月22日(木)~5月11日(火)
第2期:5月12日(水) ~ 5月31日(月)
◆ 申請期間
≪第1期≫
郵送…令和3年5月17日(月)~7月30日(金)当日消印有効
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で事務局へ
WEB…令和3年5月28日(金)9時予定~7月30日(金)23時59分
パソコンやスマートフォン等によりホームページから
≪第2期≫
令和3年5月31日(月)以降に開始予定
◆ 主な支給要件
① 営業時間:5時~21時までの営業
※ 酒類の提供は5時~20時まで
② 感染予防:業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組む
③ チラシ掲示:申請の際には、「営業時間短縮実施チラシ」または「休業実施チラシ」又はそれと同等の内容が含まれたものを掲示する
◆ 協力金の金額
2.5万円~20万円/日
※ 和歌山県ホームページを参照
◆ 申請に必要な資料
① 申請書
② 飲食店営業許可書の写し
※ 申請店舗分が必要
③ 申請店舗の外観・内観の写真
④ 営業時間短縮の実施状況が分かるもの
⑤ 申請者の本人確認書類の写し
⑥ 申請者の銀行口座通帳の写し
⑦ 宣誓書
1日当たりの売上高が83,333円以上の場合や大企業の場合
① 店舗の2019年及び2020年の売上高がわかるもの
共通:売上台帳等の帳簿の写し
法人:法人税 別表一、法人事業概況書
個人:所得税 第一表、青色申告決算書
② 店舗の2021年売上高が分かるもの
和歌山県時短要請協力金:HP
【現物給与】通勤費の非課税について
その他お知らせ
「通勤手当」には、非課税となる限度額が決められています。
限度額が超えた部分の金額が給与として課税されますので、給与の額に上乗せし源泉所得税がかかりますので、給与計算の際にご注意ください
① マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
| 2キロメートル未満 |
全額課税
|
4,200円
|
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
7,100円
|
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
12,900円
|
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
18,700円
|
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
24,400円
|
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
28,000円
|
55キロメートル以上 |
31,600円
|