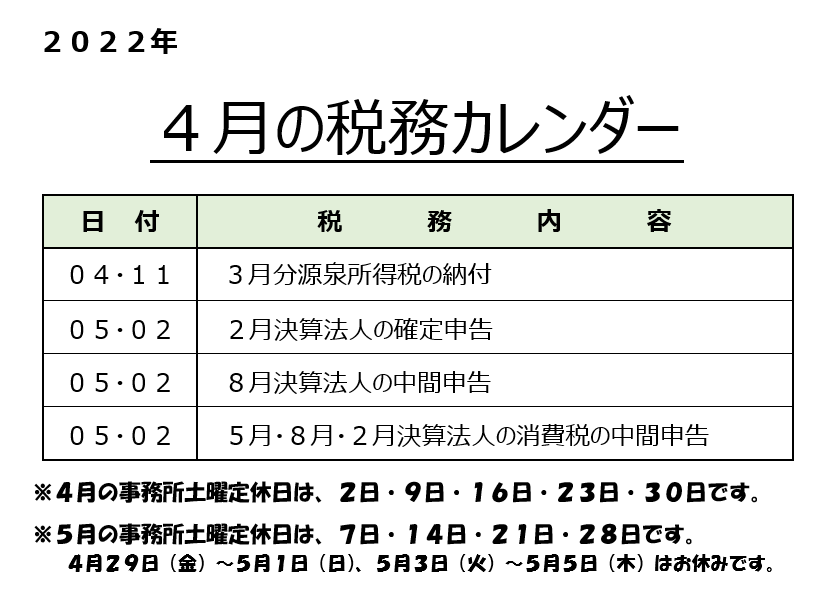今週の考える言葉「GDP」
考える言葉
GDP
日本経済の長期低迷が言われてから久しい。
「失われた10年」が20年となり、今や30年を過ぎた。日本はこれから「失われた40年あるいは50年」を歩きはじめるのではないかという経済評論家もいる。
この30年で日本はどんな変化を遂げたのだろうか?次の主な統計上の数字を見てみよう。
①日経平均株価…3万8000円台から2万9000円台へ。
②ドル円相場…1ドル=140円台から120円台へ。
③名目GDP…462兆円(1990年度)から553兆円(2021年度)へ。
④一人あたりの名目GDP…342万円から441万円へ。
⑤人口…1億2325万人から1億2618万人へ。
⑥政府債務…250兆円から1200兆円へ。(GDPの2倍超)
⑦企業の内部留保…163兆円から463兆円へ。
そこで注目したいのはGDP…。GDPとは、「Gross Domestic Product」の略で、「国内総生産」のことをいう。1年間など、一定期間内に国内で産出された付加価値の総額で、国の経済活動状況を示している。
名目GDP(553兆円)は、中国に抜かれたものの世界で第3位ある。問題は、一人あたりの名目DGP(441万円)で、世界で第25位である。つまり、人口によって経済大国としての基盤が作られてきたことを意味していると言えよう。
考えてみると、戦後の工業化による日本の経済復興をベースで支えてきたのは、地方からの集団就職、若手の労働人口(低賃金)だったと言える。そして、終身雇用制と年功序列型賃金での安定した雇用体制であった。
しかし、少子高齢化など、世の中の構造がガラリと変わった以上、過去の成功体験は全く通用しないのが今の世の中である。
また、政府債務が250兆円から1200兆円と4倍強に増えている。恐らく、景気対策のために公共投資などに使われたものと推測するが、思った以上の成果につながっていないことは明白である。
グローバル化した時代環境の中では、一国の経済政策だけでは大きな結果にはつながらないということだろう。
やはり、国を支えている国民、企業がみんなで自らイノベーションを断行し、自らの生産性を高めるために、知恵を絞り、努力をすることが大事だと考える。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」