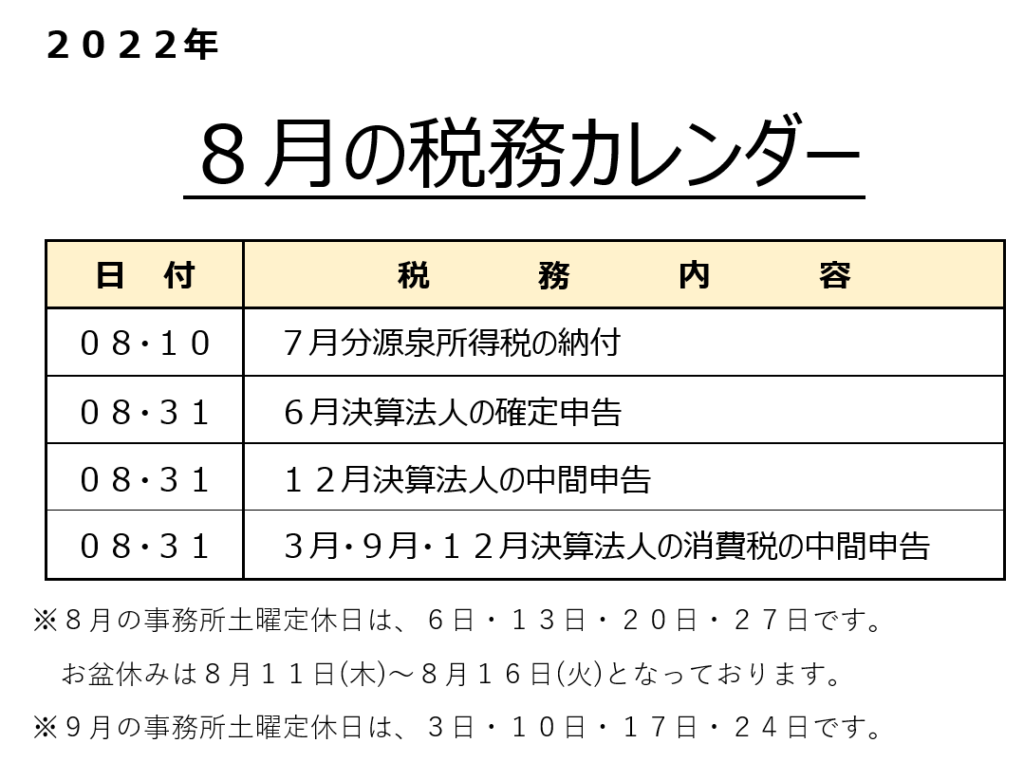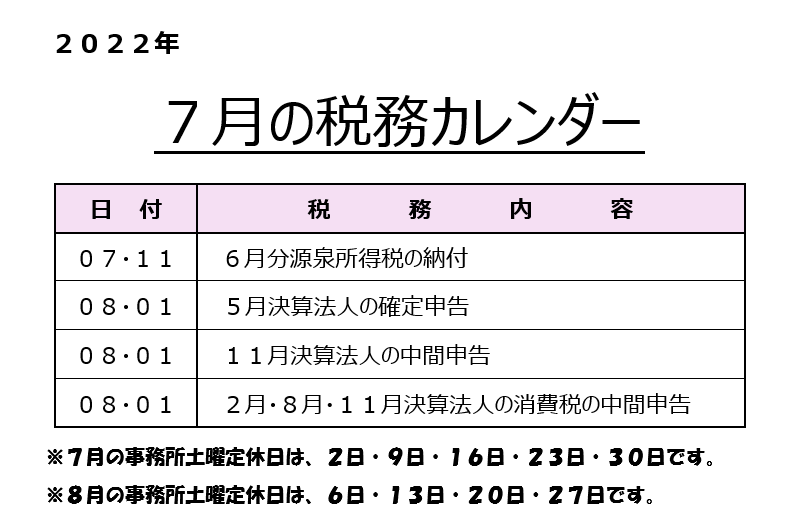今週の考える言葉「喜びの追求」
考える言葉
喜びの追求
もう、本田宗一郎氏(ホンダの創業者、1906~1991年)が逝去して30年は経つと思うが、書棚を整理しながら、本をめくっていると、氏の次の言葉に目がとまった。
「私はたえず喜びを求めながら生きている。そのために苦労には精一杯に耐える努力を惜しまない」。
人間であれば誰しも、喜びに満ちた人生を送りたいと願うだろう。その意味においては、ごく普通の願望だろう。
だが、「たえず」と念を押されると、どうだろうか・・・。さらに「そのために苦労には精一杯耐える努力を惜しまない」とまで言われてしまうと、その言葉に氏の信念、生き様を感じざるを得ないのである。
本田宗一郎といえば、豪放磊落、自由奔放などの表現をされることが多く、会社の算盤勘定や経営の舵取りは藤沢武夫氏に任せっきりで、大好きなモノづくりにハマっていたという。しかし、多くの人を魅了し、引き寄せる器の大きさがあったに違いない。
彼がいう「喜び」とは、自らの好奇心を満たすことによって得られる「喜び」だったと思うし、さらに、自分のモノづくりの成果が世のため人のためになる、つまり他人の喜びと通じるという確信だったに違いない。
氏の価値観(思考の枠組み)が「自利利他の精神」で培われていたことは、次の言葉においても自明であろう。
「私は若い社員に、相手の人の心を理解する人間になってくれと話す。それが哲学だ」と。
生前に、本田宗一郎氏と親交が深かった井深大氏(ソニーの創業者)は、彼の書籍『わが友本田宗一郎』の中で、本田氏を評して次のように述べている。
「私が、本田さんを高く評価している点は、大きくいって二つある。ひとつは、技術者としての志の高さというか、完璧なエンジンづくりを目指した姿勢である。もうひとつは、会社のことだけでなく、広く世の中のことや、みんなが上手に幸せに暮らしていけることをつねに考え、ほんとうの意味での真理を自分でできることで実行し、一生を貫いた存在だった」という。
「温故知新」という言葉があるが、本田宗一郎氏や井深大氏に関する本を読み直していると、今再読し、要約文を作成しているP・F・ドラッカーのマネジメント思考を、すでに実践し成果を出した経営者が日本にはたくさん存在していたことを、改めて思い知らされる。
ドラッカーが生前、日本によく訪れて、日本びいきだったことが思い出される。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」