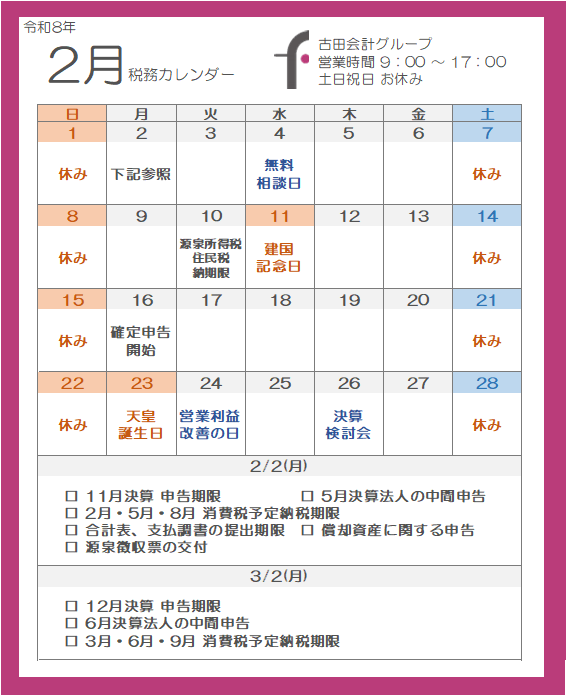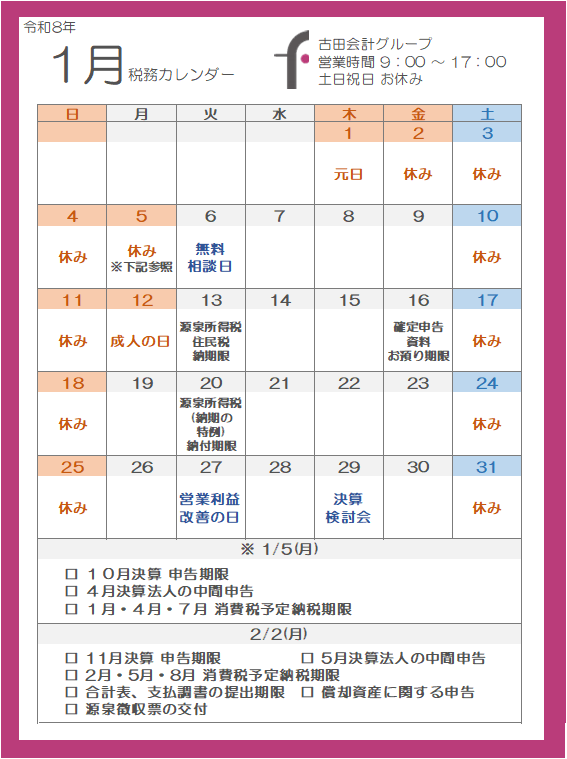今週の考える言葉「健全経営」
考える言葉
健全経営
昨今、組織力の強化、すなわち“健全経営”の強化が叫ばれている。その背景には、大きく、次の二つの要素がある、といわれている。
(1) 事業環境の変化・多様化
つまり、不確実性時代(VUCA)への突入である。
VUCA(ブーカ)とは、先行きが不透明で、将来の予測が困難になっている状態の要素を示す造語である。
➀ Volatility(ボラティリティ):変動性
② Uncertainty(アンサートゥンティ):不確実性
③ Complexity(コムプレクシティ):複雑性
④ Ambiguity(アムビギュイティ):曖昧性
(2) 働き方や人材の多様化
「働き方改革」の推進による労働時間の見直しや削減、コロナ感染の拡大によるテレワークの増加、DXも急激に発展している。また、グローバル化に伴い、制度変更が進み外国人労働者の増加などで、人材も多様化している。
組織論で有名なチェスター・バーナード(1886~1961、米)は、組織の成立条件として、次の3つの条件を掲げている。
① コミュニケーション(組織内で情報を共有し、意思疎通を図ること)
② 貢献意欲(組織メンバーが互いに一緒に働いて相手の役に立ちたいと思うこと)
③ 共通目的(共通の目的を持つことで、組織の協調性が生まれること)
では、“健全経営”を推進し、組織力を強化するためには、ドラッカーがいう「目標管理の徹底」であろう。
① 企業理念やビジョンの浸透(共通目的)
② 経営計画の共有(共通目標)
③ 業績の公開
④ 計数の強い人材の育成
⑤ 強いリーダーシップ
⑥ 機能する人事評価制度の構築と浸透
⑦ エンゲージメントの向上
⑧ やりきる風土(MAS監査・未来会計の徹底)
“健全経営”について、いろいろ述べてきたが、先ずは病気にならない企業体質、つまり健康管理を怠らないことである。
そのためにも一度、自社の未来をじっくり考える一日、『将軍の日』に参加して欲しい。
転載元:IG会計グループ 「考える言葉」